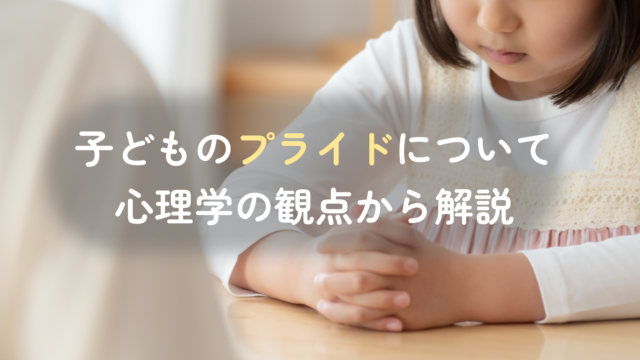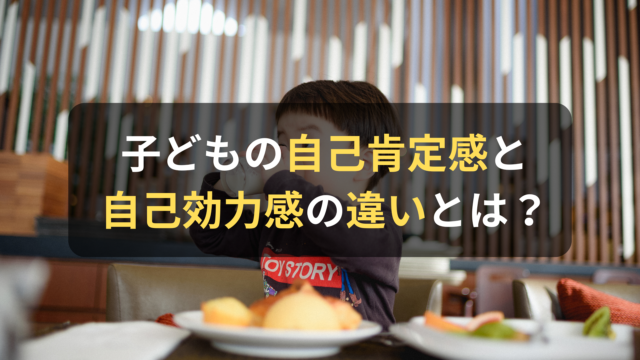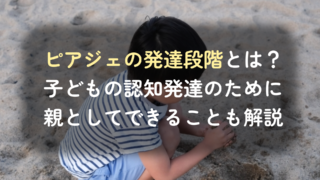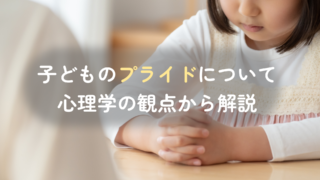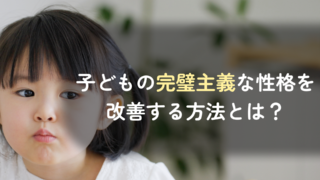「子どもが人見知りで悩んでいる」「友達ができると良いけど、うちの子は人見知りなのでちょっと不安」といった親の声をよく耳にします。
同時に、「心配していたけど成長するにつれて人見知りが軽減された」という方もいるように、時間の経過とともに人見知りが改善されることもあります。
本記事では、子どもの人見知りはそもそも直さないとダメなのか、人見知りを克服させるために親には何ができるのかを解説していきます。
子どもの人見知りが過度である場合は改善が必要

人見知りが短所ではないとはいえ、過度な人見知りは社会での生活を難しくする可能性があります。特に今のVUCA(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)と呼ばれる変化の激しい時代や、人生が100年とも言われる長寿社会においては、生涯同じ環境にいるということはなくなっていくでしょう。
時代の変化に適応し、新しい環境や人々との交流が不可欠であり、そのためには、コミュニケーション能力が非常に重要になります。
自分の意見を恐れずに主張する力、他人と打ち解ける能力、良好な人間関係を築くスキルは、これからの社会で生き抜く上でも欠かせません。過度な人見知りがあると、これらのスキルを身につけることが難しく、生きづらくなる可能性があります。
そのため、子どもの人見知りが気になる場合は、子どものうちからトレーニングし、改善するようにしましょう。
人見知りとは、新しい人や環境に心理的な抵抗を感じる状態

フンボルト大学心理学者ジェンズ・ビー・エーセンドープフ氏が発表した論文によると、「人見知り」は多くの場合、新しい人や環境に対して心理的な不安や恐怖を感じ、その結果として他人とのコミュニケーションや社交的な関わりを避ける傾向がある状態を指します。
このような人見知りが発生するのは、恥や拒絶に対する恐怖心が原因として考えられます。例えば、新しいクラスになると「話しかけても無視されるかも」「断られるかも」という不安が自分から話しかけるのを難しくします。
特に子どもが置かれる環境では、毎年クラス替えがあったり、習い事を始めたりと新しい環境への移り変わりが多く、この心理状況(人見知り)が起きやすくなります。
一方、慣れることでこの人見知りの傾向は軽減するということがわかっています。そのため、年齢を重ねるにつれて何度も新しい環境に慣れていくことで徐々に人見知りも改善されていくと考えられます。
それに加えて、一人でいることが好きで積極的に関わらない子どももいるので、注意深く様子を見て、必要に応じてサポートしてあげましょう。
参照:
子どもの人見知りを改善する3つの方法

時間や経験とともに改善されていくとはいえ、人見知りの程度には個人差があります。
子どもの人見知りを改善するための方法としては、小児社会効果療法(Social Effectiveness Therapy for Children:SET-C)がとても効果的であると言われています。ここからは、この小児社会効果療法をもとに、家庭でもできることを解説していきます。
人前で話す経験を積ませる
人前で話す機会を作ることで人見知りを改善できると考えられています。具体的な方法について以下で解説します。
・小さなグループで話すことになれる
トピックは子どもが興味を持つものや共感できるものを選ぶようにしましょう。これにより、子どもは自分の意見や考えを表現し、他の人の意見を聞く練習をすることができます。第一ステップとして、まずは家族で行ってみるのもおすすめです。比較的安心して話すことができるので、人見知りの子どもでも自分自身の感情を表現しやすくなるでしょう。
・新しい環境に備えてロールプレイングをする
子どもたちに異なる役割を与え、その役割に基づいて対話やシチュエーションを演じさせます。例えば、「新学期のクラス替え。席が隣になった新しい友達に、どのように話しかけるか」など、子どもが学校などで直面するであろう具体的なシチュエーションを設定してみるのがおすすめ。演じることを通じて、様々な社会的な状況に対処するスキルを養います。
いきなり他人の前で話すのはハードルが高いと感じる場合、こちらもまずは、家族の前で同じような内容を試してみるのも良いでしょう。
子どもをしっかり褒め、安心感を与える
上記の「子どもに人前で話す経験を積ませる」を実施した上で、今度は子どもをしっかりと褒めてあげるように心掛けましょう。
「人前で話すことはすごいことだよ」「失敗すること自体が貴重な経験になるんだよ」と子どもを励まし、安心感を与えてあげることが大切です。ステップ1の行動に対して、親が肯定的なフィードバックをすることで、子どもは自然と自信を付け、徐々に人見知りを克服していきます。
ポジティブになれる言葉をかけて、挑戦を手助けする
もし、ロールプレイングなど十分な準備をしても、子どもが不安やストレスを感じている場合には、子どもがポジティブで前向きになれるような声を掛けてあげましょう。
例えば、子どもが「明日から初めて一緒のクラスになる人に話しかけられるかな」と不安な気持ちになっている場合は、「あなたは皆に好かれるタイプだから、きっと大丈夫だよ」と声をかけてみることで、子どもが勇気を出す手助けになります。
また、「失敗しそう」とネガティブになっている子どもには、「この前練習したから大丈夫だよ」など、現実的でかつ肯定的な言葉に置き換えて励ましてあげることも大切です。そうすることで、自分の能力や直面する状況について、より前向きで現実的な見通しが持てるようになります。(参考:認知行動療法(CBT))
参考:
子どもの人見知りは決して短所ではない

人見知りの我が子を目の当たりにすると、子どもにもっと社交的になってほしいと願う親は多いかもしれません。しかし、子どもの人見知りは決して短所ではありません。
フロリダ中央大学の研究によれば、人見知りを発揮するような子どもは以下のような強みがあることがわかっています。
・一人の時間を大切にし、深く考えることが得意
・繊細で感受性が高いので、他人の感情を敏感に感じ取ることができる
・観察力や洞察力が優れている傾向があり、創造的な考えを生み出す
・自己に対する理解が深く、内面的な成長を促進する
このように、人見知りだからといって決して短所ではないということを知っておきましょう。また、子どもの人見知りは、これからあらゆる経験をしていく中で改善されることもあるので、親として、気長に成長を見守ることも大切です。
参照:
まとめ

子どもが環境の変化によって人見知りしてしまうことはよくあることです。でもご安心ください。人見知りの程度は個人によって異なりますが、一般的には時間と経験によって緩和されることが多いです。
特に子どもの場合、新しい環境や人々に慣れ親しむことで、徐々に人見知りの傾向が減少していくことがあります。もし子どもの人見知りが過度に強い場合や、どうしても気になる場合には、心理的なサポートや適切な環境づくりを通じて、子どもの自信をつけるお手伝いをしてみることをおすすめします。親としてのサポートが、子どもの成長の支えになるはずです。