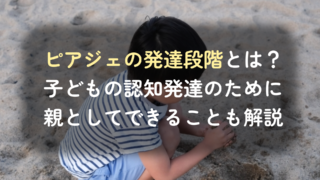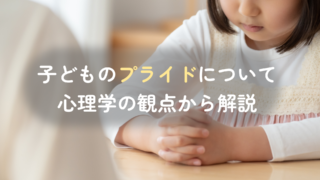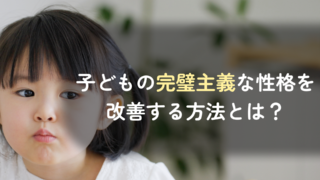子育てをしている中で「もしかして、私、過保護なのかな。」「子どもに過干渉しているかも」と不安になることがあるかもしれません。
子どもに対して過保護や過干渉な育児をしてしまうことで、子どもに悪影響を与える可能性もあります。
今回は、過干渉や過保護が子どもに与える影響について解説し、どのように子どもに接するべきかについて解説します。
「過干渉」と「過保護」の違いとは

そもそも、過干渉と過保護ではどのように違うのかについて解説します。
過干渉について
過干渉とは親や保護者が子どもの生活の細部に至るまで干渉し、子どもから意思決定や選択の自由を奪ってしまう状況を指します。
例えば、子どもが友人と遊びにいく時や学校の科目選択など、子ども自身の意思決定を必要とする状況で過干渉は起こりえます。親が子どものためにすべての決定を下してしまうと、子どもは自分の選択を信じることや、困難に直面したときに自分で解決する機会を失う可能性があります。
ロチェスター大学の研究では、子どもたちの成長や発達においては、親が一方的に子どもの行動に介入するよりも、子どもたちが自発的に自分のやりたいことをする雰囲気を作ることが重要であることがわかっています。
例えば、親が子どもの友人関係や学校生活について質問する場合、細かな質問を重ねて情報を引き出そうとするよりも、むしろ自然な会話の中で子どもが自ら話したいと思えるような雰囲気を作ることが大切です。
親が子どもの話をじっくりと聞き、理解しようとする態度があれば、子どもも自らの経験や感じたことを親に話すでしょう。
また、子どもが自分のことを話すことに対して安心感を持てるよう、批判や否定ではなく、理解と受け入れの姿勢を持つことが重要です。
これは、子どもの主体性を促すとともに、親子の信頼関係を深めることにつながります。
過保護について
過保護とは親が子どもを過度にリスクや困難から遮断しようとする状況のことを指します。これは子どもが自立するために重要な経験を遠ざけてしてしまう可能性があります。
例えば、子どもが友達との間でトラブルに直面した場合、親が過度に介入し、率先して解決しようとすると、子どもは自分で問題を解決したり、対人関係のトラブルにどのように対処すべきかを学ぶ機会を失うことになります。
ダルハウジー大学が発表している研究によれば、過保護な傾向がある親は、子どもがリスクや責任に直面する機会を与えられないため、子どものレジリエンス(逆境に対する適応力)の成長を阻害する可能性があることが示されています。
親としては子どもが困難に直面したり、ストレスを感じさせないように、子どもからあらゆる問題を避けたいという気持ちは理解できます。しかし、その結果として、子どもが自分自身の能力を信じることができない、または新たな試みに対して恐怖感を持つようになる可能性があります。
親としては、子どもが自分で解決策を見つけ出したり、問題解決のスキルを育てる機会を提供することが大切です。
子どもにはどのようなことを意識してサポートするべきか

子どもを思うばかりに過保護や過干渉になってしまいがちですが、子どもとベストな関係性を作るためにはどのようなことを意識するべきかについて、先ほどのロチェスター大学の内容をもとに以下で解説します。
1. 子どもの行動の動機や感情について考える
研究によれば、子どもの行動の動機や感情を理解し、受け入れることが重要といわれています。
例えば、子どもが何かの意図を持って行動を起こしたときに、それをすぐに否定したり、改善しようとするのではなく、「そもそもなぜ子どもはそのような行動をとったのか?」の行動の源泉を探るべきです。
子どもの行動にも何かしらの理由や、それを起こそうと思った感情があるはずです。
例えば、子どもが親の手伝いをしたいと思い、部屋の掃除を自分で始めた場合を想像してみましょう。慣れない掃除で失敗して散らかってしまったのを見て、親は自分でやった方が早いと思うかもしれません。
しかし、それでは子どもが自分で起こした失敗を解決する経験を奪うことになったり、自分の気持ちを尊重されないという意識を芽生えるきっかけにもなるかもしれません。
まずは、なぜ掃除しようとしてくれたのかの子どもの意図を尊重し、適切な方法を教えてあげましょう。
2. ルールを決めて、その範囲内で子どもに主体的に活動するように促す
子どもの行動などに無意識に介入してしまう場合、ルールを決めることもまた有効とされています。子どもとルールを決めて、その範囲内で子どもが主体的に動ける環境を作ることで、子どもは自分で判断することができます。
子どもが友達と遊ぶときは「門限は5時までに帰ってくるようにする」「川や海など危ないところには近づかない」などのルールを決めて、その理由についても子どもに説明し、納得させましょう。
ルールを設定するだけではなく、子ども自身もそれに従う必要があると感じることが重要です。一方で、細かすぎる、厳しすぎるルールは逆効果にもなるためバランスが重要です。
3. なるべく子どもに選択肢や機会を与える
先ほどのルールの話にも付随しますが、細かすぎるルールは子どもが自分で選択する力を奪う可能性もあるため、なるべく子どもがあらゆる選択肢から自分の意志で選べるようにしましょう。
「あれは危ないからやったらダメ」「これはこんなデメリットがあるからダメ」などと、ちょっとしたリスクに過剰に反応し、選択肢を奪うことは子どもにとってよいとはいえません。
近年、公園から遊具がなくなったり、近所迷惑になるからとボール遊びなどができない環境も増え、子どもにとっていろんな経験をするチャンスが大人の都合や価値観で取り上げられてしまっている状況もあります。
最初から禁止にされてしまうと、子どもはどのような状況で迷惑をかけるのか、怪我をしてしまうのかを知る機会がなくなってしまいます。過度に危険な行動や遊びは避けるべきですが、「危ないことを知る」「迷惑をかけてしまうことも知る」ということもまた子どもの成長において重要です。
最初から選択肢を限定せず、子どもにも学ぶ機会を提供することを意識しましょう。
まとめ
過保護や過干渉になってしまうことは親として大切な子どもを思うばかりに起きてしまうことですが、子どもの未来を考えると、その瞬間の感情や衝動をグッと堪えて、子どもに「自分で試してみる」という経験も提供しましょう。
子どもも自らリスクに直面することで、将来的にたくましく、主体的な人に育つことでしょう。