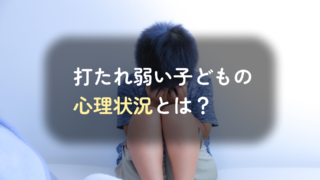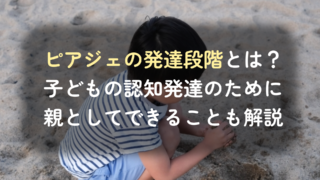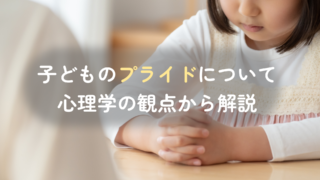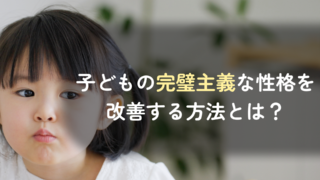「子どもが全然我慢しない。」「このまま分別がつかず、わがままな大人になったらどうしよう。」と悩む方も多くいらっしゃるかと思います。
子どもの我慢強さを育てるためには、厳しくするだけでは効果が生まれにくく、適切なトレーニングが必要です。
今回は子どもの我慢強さが将来どのような場面で役に立つのか、子どもの我慢強さを育てるために必要な考え方について紹介します。
我慢強さは社会でも重要な素質

子どもに対して「今は我慢してほしいな」と思う瞬間がありますよね。しかし、我慢することを厳しく指導し続けるのは精神的にも疲れる作業でもあります。
ライフネットが実施した調査によると、新社会人に必要な3つの要素として、「協調性があること」(45.6%)、「素直であること」(34.6%)、「向上心があること」(33.7%)がトップ3にランクインしており、「我慢強いこと」が上位4つ目に上げられていました。
この調査結果からもわかる通り、我慢強さは社会人にとって重要な素質であり、社会で活躍する上で大切な土台となるため、早いうちから訓練するのがよいでしょう。
我慢強さを育てることによる将来的なメリット

最近の時代では、「我慢を強要せず、のびのびと育てる」という風潮が少しずつ浸透していますが、今も昔も、社会に出ると我慢をするべき瞬間は非常に多くあります。
のびのびと育てることも重要ですが、同時に我慢強さを鍛えることで、将来的にどのようなメリットがあるのかを、バークレー大学のOzlem Ayduk氏による研究をもとに紹介します。
問題解決能力が高くなる
「辛い」や「イライラする」などのネガティブな感情をコントロールできる人は、ストレスによる衝動的な行動をコントロールし、問題解決をより簡単に実行できるといわれています。
例えば、子どもが友達と遊んでいる時に、その友達がつい言ってしまったネガティブな言葉に対して、感情的になり、衝動的に怒鳴ってしまうかもしれません。
しかし、自分の感情を適切にコントロールできるようになれば、一旦感情を落ち着け、なぜそのような事態になったのか、自分がどのように対応すべきかを冷静に考えることができ、ベストな解決策を選択することができます。
長期的な人間関係の構築ができるようになる
子どもの頃から満足遅延耐性(Delayed Gratification、DG)が高い人は、他者から否定されるなどの状況に直面した際に、自分を冷静に保つことができるということが示唆されています。
満足遅延耐性とは、すぐに報酬を得ようとせず、より大きなメリットや長期的な目標を達成するために我慢する能力のことを指します。
例えば、満足遅延耐性が高い子どもが友人からの不公平な扱いに直面したとします。その子は直感的に怒りをぶつける代わりに、その状況を冷静に見つめ直すことができます。
友人がどうしてそのような行動を取ったのか、その背後には何があるのかを理解しようと試みるかもしれません。
このように子どもが異なる視点で解釈をすることで、怒りの衝動を抑え、友人との間に発生した問題を解決するためのより良い解決策を見つけることができ、結果として、人間関係の改善につながります。
これは子どもから大人まで、人生を通して重要なスキルと言えるでしょう。
健康的な食習慣が定着する
我慢強さは食事管理にも直結します。上記の研究によれば、我慢強い子どもは肥満になるリスクを減らし、食生活に良い影響を与えることが示されています。
例えば、子どもがスーパーのお菓子コーナーでポテトチップスを見た時、我慢強い子どもは、一時的な満足感を選択することは長期的に見て健康に悪影響を与えることを理解しています。
そのため、子どもはその誘惑に耐えることができ、より健康的な食品を選ぶことを選びます。
このような健康的な食習慣は、将来的には心臓病、糖尿病、高血圧などのリスクを軽減します。子どもの頃から我慢強さを訓練し、健康的な食習慣を形成することが重要です。
参考:
Regulating the interpersonal self: Strategic self-regulation for coping with rejection sensitivity
Preschoolers’ Delay of Gratification Predicts Their Body Mass 30 Years Later
子どもの我慢強さを伸ばすための方法

それでは子どもの我慢強さを鍛えるためにはどのような方法が適切かについて、先程のバークレー大学の研究をもとに解説します。
遅延報酬スキルを伸ばす
子どもの我慢強さを伸ばすために、遅延報酬スキルを伸ばすという考え方があります。
遅延報酬スキルとは、今すぐ手に入る報酬を我慢し、将来の大きな報酬を得る能力のことを指します。この能力を持つ子どもは、自分をコントロールする能力や計画性、目標設定スキルを向上させる傾向があります。
また、遅延報酬スキルは、学業成績や人間関係の質、健康などの面でも良い結果と関連していることが研究で示されており、子どもの発達において重要な要素となります。
遅延報酬スキルを育てるためには、子どもが自分の行動とその結果の間の関係を理解すること、例えば子どもが今すぐ宿題を終わらせておくことで、その後の遊びの時間が増えるといったことを体験させることが重要です。
意図的に興味を紛らわせる
我慢強さのコツの一つに、子どもが持っている興味を意図的にそらせることで、目の前のことを我慢できるようになります。
例えば、子どもが欲しがっているお菓子が目の前にあるものの、それをすぐには食べることができない状況を考えてみてください。子どもにとっては苦痛を感じる状況でしょう。
しかし、この状況で目の前の関心ごとを別の楽しいことなどに集中することで、お菓子を待つ時間も楽しく過ごすことができます。
子どもがお菓子の時間を待つ間に、自分の好きなアニメを見たり、別の楽しいことで遊んだりすることで、すぐにお菓子を食べたいという衝動を抑えることができます。結果として、子どもが我慢に伴う苦痛を軽減しながら、うまく乗り越えることができるのです。
これらは勉強や人間関係など、日常生活の多くの側面でのパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。注意制御能力は、子どもの頃から身につけることができ、成長するにつれて発展します。
認知的再構成
目の前の誘惑を「クールダウン」するために「認知的再構成」も我慢強さを促進します。
認知的再構成とは、自分が物事をどのように考え、解釈するか、つまり自分の「思考の枠組み」を再構築し、変えることを指します。
例えば、子どもがコンビニで見つけた大好きなポテトチップスを買いたくなったとします。その瞬間、子どもはそのポテトチップスがどれだけおいしいかを想像すると思いますが、その場で購入しないという選択をするためには、そのポテトチップスの誘惑を「クールダウン」する必要があります。
ここで認知的再構成が役立ちます。子どもは、そのポテトチップスをただのじゃがいもの薄切りと捉え直すことで、それに対する欲求を減らすことができるかもしれません。このような方法で、子どもは自分の欲求を制御し、より理性的な選択をすることが可能となります。
この認知的再構成は、食事制限や禁煙など、様々な場面でも効果的です。
参考:
Regulating the interpersonal self: Strategic self-regulation for coping with rejection sensitivity
まとめ
我慢強さを育てるには、ただ厳しくするだけではなく、子どもの状況に応じて今回紹介したアプローチを実践してみるのがよいでしょう。
我慢することを子どもの頃から身につけておくことで、将来大人になってからも社会から求められる人に成長することが期待できます。